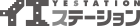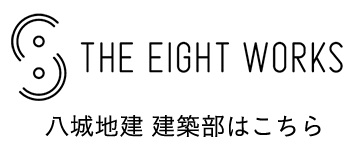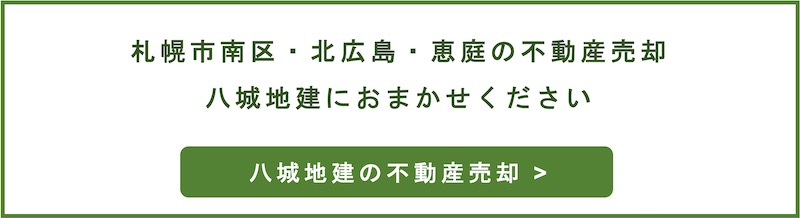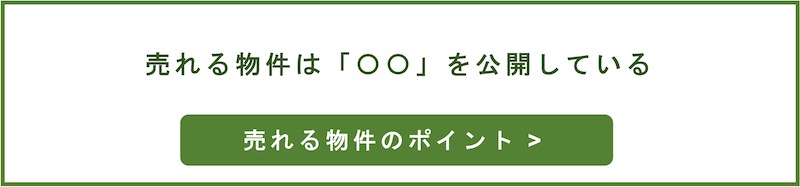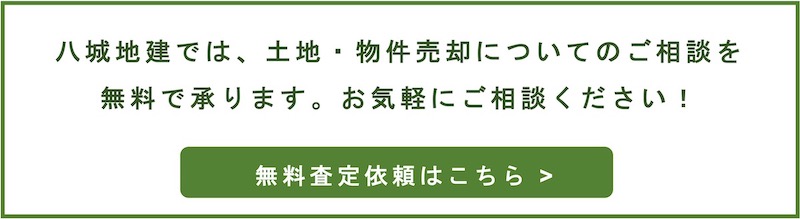二次相続で不動産はどうなる?税負担とトラブルを防ぐ対策
2025.09.10
こんにちは!不動産売買をサポートする八城地建の酒井です。
「両親が相次いで亡くなったとき、不動産をどう分ければ良いのだろう」
「二次相続では税金が高くなると聞くけれど本当?」
そんな疑問や不安を抱いていませんか?
実際、二次相続は一次相続に比べて控除が少なくなり、相続税の負担が大きくなりやすい傾向があります。
さらに、不動産は現金のように分けられないため、兄弟姉妹の間で意見が対立しやすく、トラブルにつながることも少なくありません。
今回は、二次相続が不動産に及ぼす影響と、相続時に困らないための対策をわかりやすく解説します。

二次相続とは?不動産がある場合にどんな影響が?
二次相続とは、両親のうち一人が亡くなった後、残された親も亡くなったときに発生する相続のことです。
この場合の相続人は原則として子どものみで、両親の財産を子ども世代で分け合うことになります。
二次相続では、一次相続よりも税負担が大きい傾向がある
一次相続と二次相続では、相続税の負担に大きな差が生じやすいです。
主な理由として、一つは基礎控除が小さくなること、もう一つは配偶者控除が使えないことが挙げられます。
①基礎控除額が小さくなる
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。
二次相続では配偶者がすでに亡くなっているため、相続人は子どものみとなり、一次相続よりも人数が減るケースが一般的です。
相続人の数が減れば控除額も小さくなり、結果として課税対象の金額が増えやすくなります。
②配偶者控除が使えない
一次相続では配偶者に相続させれば最大1億6,000万円まで非課税にできる「配偶者控除」が利用できます。
しかし、二次相続では配偶者がいないため、この大きな優遇は使えません。
そのため課税対象額が増え、相続税を支払う可能性が高くなります
このように、二次相続は一次相続に比べて控除が少なくなるため、結果的に税負担が大きくなりやすいのです。
二次相続で不動産がある場合に想定される影響
不動産を含む二次相続では、相続人同士のトラブルが起こりやすいことや、納税スケジュールへの影響などが想定されます。
兄弟姉妹間で利害がぶつかりやすい
一次相続では「配偶者がそのまま住み続ける」という形で不動産の扱いが決まることが多いのに対し、二次相続ではその前提がありません。
相続人である兄弟姉妹の中で、誰かが住み続けるのか、それとも売却して現金化するのかを話し合う必要があり、その判断をめぐって意見が分かれやすくなります。
共有名義のまま残され、将来の処分が難航する可能性がある
不動産は現金のように均等に分けられないため、合意がまとまらないまま共有名義で相続されることがあります。
共有状態では売却や活用に制約が多く、いざ処分しようとしても全員の同意が必要になるなど、将来にわたって大きな負担となる可能性があります。
相続税の負担と納税資金確保のハードルが上がる
一次相続であれば配偶者控除によって税負担を抑えられますが、二次相続ではこれが使えず、課税額が大きくなりやすいのが特徴です。
特に不動産は現金化しない限り納税に充てられないため、兄弟姉妹間の調整が長引くと売却が遅れ、納税期限に間に合わないリスクが高まります。
相続した不動産を売却する流れは、「相続した不動産を売却する流れを解説!揉めないための方法や節税対策も」で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。
不動産の二次相続で困らないために対策を!

二次相続では、相続人が子どものみとなるため、税負担が重くなりやすく、不動産をめぐって揉める可能性も高まります。
ですが、事前に準備をしておけば、家族が困る事態を避けられます。
ここでは代表的な対策を5つ紹介しましょう。
1.生前に不動産を売却して現金化する
将来住む予定のない不動産は、生前に売却して現金化しておくのがおすすめです。
現金なら均等に分けやすいため、子ども同士のトラブルを防げます。
また、納税資金としてすぐに使えるので、申告期限に間に合わないリスクを減らせます。
相続した不動産に住まない場合、固定資産税や管理費の負担がなくなるのも大きなメリットです。
なお、売却して得た現金は相続時に預金として残すと課税対象になるので、税金を減らすために生命保険に充てる方法もあります。
なかでもよく利用されるのが「一時払い終身保険」で、まとまった資金を一度に保険料として払い込み、死亡保険金として相続人に残すことが可能です。
生命保険の死亡保険金には「法定相続人1人あたり500万円まで非課税となる特例」があるため、預金で残すよりも税負担を抑えられる可能性があります。
なお、実際に今売り出せばいくらになるのか、いくらで売れるのかという市場での価格(実勢価格)は、不動産会社にしかわかりません。
売却を検討する場合は、不動産会社に査定を依頼しましょう。
不動産会社の選び方については、「不動産会社の選び方を解説!売却する場合はどう選ぶべき?」で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてくださいね!
2.遺言書を作成し、定期的に見直す
親が元気なうちに遺言書を作成しておけば、相続の方向性をはっきりさせることができ、「誰が住むのか」「売却するのか」という相続人同士の争いを防ぎやすくなります。
財産の分け方の理由も添えておくと、納得感が高まるでしょう。
また、不動産の価値や家族の状況は時間とともに変化するため、遺言書は一度作ったら終わりではなく、定期的に見直して更新しておくことも大切です。
3.一次相続で配偶者の相続分を調整する
一次相続で配偶者にすべてを相続させると、その時点では税負担を抑えられますが、二次相続の際に課税対象の財産が増え、子ども世代の税負担が大きくなる恐れがあります。
そのため、配偶者の生活資金を十分に確保した上で、余裕分を子どもに相続させておくと、将来の二次相続に備えたバランスのよい分配になります。
ただし、どの程度分けるかは家庭の状況によって異なるため、税理士などの専門家に相談しながら配分を決めると安心です。
4.小規模宅地等の特例を活用できる環境を整える
自宅の土地については、条件を満たすと「小規模宅地等の特例」により相続税評価額を最大80%まで減らせます。
評価額が下がれば、それをもとに計算される相続税も大幅に軽くできます。
二次相続でこの特例を使うためには、相続が始まった時点で子どもが親の自宅に同居し、そのまま住み続けている状態であることが基本条件になります。
そのため、事前に以下のような準備をしておくと 二次相続時の税負担軽減につながります。
- 子どもが親と同居して生活する
- 二世帯住宅に建て替えて、親子が暮らせる環境を整える
- 一次相続の段階で、同居している子どもに自宅を相続させておく
- 配偶者居住権を活用して、居住権を配偶者から子どもへ引き継ぎやすくする
5. 相次相続控除を活用する
一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合には、「相次相続控除」により、一次相続で支払った相続税の一部を二次相続の相続税から差し引けます。
短期間に相続が重なることで相続人の税負担が過大にならないように設けられた制度です。
控除額は、一次相続からの経過年数に応じて計算されます。
具体的な要件や計算方法については、国税庁の「相次相続控除」の解説をご確認ください。
実際の申告にあたっては専門家に相談し、適用を漏らさないようにすることが大切です。
二次相続における不動産対策は早めの準備が重要
二次相続では、相続税の負担が重くなることや、相続人同士が不動産の分け方をめぐって揉めることなど、さまざまな問題が起こりやすくなります。
特に不動産を所有している場合は、納税資金の確保や分割方法の調整が難しいです。
リスクを避けるには、生前に不動産を売却して現金化する、遺言書を作成して分割方法を明確にしておく、小規模宅地等の特例を活用するなど、いくつか有効な対策があります。
制度の理解や手続きが複雑なため、税理士や不動産会社といった専門家に相談しながら進めると安心です。
札幌市南区、北広島市、恵庭市で不動産の売却を検討している方は八城地建まで、お気軽にご相談ください!
ご相談は無料で承っています。